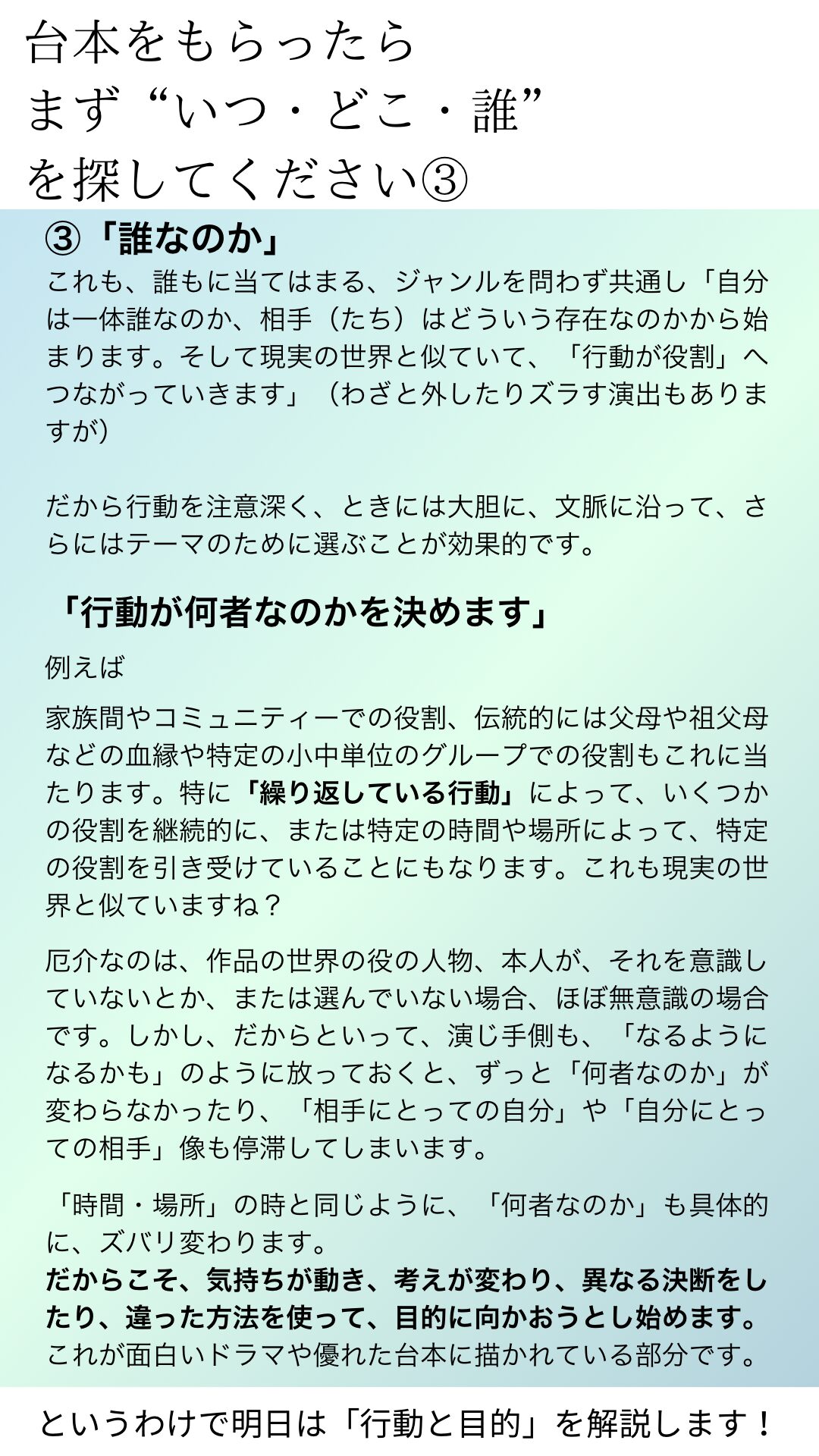オーディション準備で、春は急な展開!本領発揮の演技コーチ、鍬田かおるです。
オーディション用の演技プラン、うごきの振付、現場のトラブルシューティング、1人で悩まずご相談ください。
さて、本日は、つい先延ばしにしてしまう方も多いが、面白くなるかならないかに関わる重大な根本!
その違和感、見逃さないで!
現場やオーディション、稽古をしていて、「セリフがどうもしっくりこない」
「自分事にするのに時間がかかる・・・」
「相手とのやりとりが、何か噛み合わない」
と感じることはありませんか?
その違和感の正体は、多くの場合、演じている人物が「誰なのか」がまだ掴めていないことにあります。
かつての私も、若かったとはいえ…
自分の役が脳外科医だという職業設定は理解していたのですが、具体的な数字に欠けていて、その仕事のプレッシャー、その仕事に就くまでの困難な道のり、数多くの犠牲、その時代ならではの科学の発展と問題点、職場及び仕事そのもののストレス、身体的な条件と健康状態、人間関係と最大の恐怖…..などに考えが及ぶようになったのは、その公演が終わってからでした…。
素晴らしい名作だったのに、単なる「印象やイメージ」だけで演じていたこと、本当に、恥ずかしい限りです。今でももったいなかったなぁと、残念に感じています。
さてこの「自分は一体誰なのか、そして相手(たち)は自分にとって誰なのか」は
人物設定の細部やキャラクターの性格という話ではなく、
「自分にとって相手は誰なのか」「相手にとって自分は誰なのか」ですから、
当然、非常に個人的、かつ、心理的なリアリティーと言っても過言ではない、“関係性”や“役割”の次元の話です。
「なぜそんなに、誰なのかが大事だって言うの?」とおっしゃる方は
「あなたが作品の中で行動を通して見えたり聞こえたりするようにしている、役の人物は、一体何者なんですか?」と置き換えてみてください。
つまり「正体」です。
(必ずしも犯人と言う意味ではありません、人間として何者なのか、どういった本質的な要素があるのか、ということです。)
そしてこれは、演劇、映像、歌唱、朗読、さらには身体表現やダンスにおいても共通する、最もベーシックかつ見落とされがちな出発点です。
20年以上、演技指導とムーブメントの現場で向き合ってきて感じるのは、
すでに力のある俳優ほど「自分がどんな役割を担っているか」、「この役が明らかにするのは…」
を明確にし直すことで、次のレベルに進んでいくということです。
特に素晴らしい方は、キャスティングの段階からとてもこういった点を意識していらっしゃいます。
何年続けていても、ここの解像度が変わると世界が変わります。
台本読解の鉄則ーこれは私が一緒に、イギリスの演劇学校で学んだ名優たちや、ハリウッドスター、世界の巨匠も同じなので信じてください。
脇道にそれずに取り組めば、結果は後からついてきます。
1:「誰なのか」なまま曖昧だと、セリフが浮いています
単なるプロフィールじゃなく、“関係性”と“役割”が鍵!
かつて、私の職場であった、老舗の劇団でも
役の履歴書を書くとか、プロフィールを作ってみようという極めて伝統的な世界中で応用されている入り口に、「それは古いやり方だから」と一蹴した中堅?演出家がいらっしゃいました。
そしてその方の大先輩でもあり、脚本家としても優秀な方のほうが「そういうのに、古いとか、ないよね。基礎だから。」とおっしゃった。その時、その先輩の目は笑っていなかった。けれど、うっすら口元が笑いながら、つぶやいていたの覚えています。怖い!!
・・・
全くその通りなんです。
・・・
こういう根本の部分は、古いも新しいもなく、
私たち人間が、小さな単位かのグループへ、中サイズのコミュニティーへ、そして社会を構築している以上、「誰なのか」、「自分の役割とは?」「何を期待されている?」に代表されるような関係性は、アイデンティティーの1部でもあり、無視しては通れないものです。
(これを無視したかったのは、一体何なのかな…)
ともあれ!
演技の文脈で「誰なのか」とは、単に名前や職業、年齢といった外的なプロフィールを指すのではなく、
「このシーン、この瞬間に、自分はどんな立場にいて、誰との関係性の中にいるのか」
を見極めることを指します。
これは、ジャンルを問わずすべての作品において当てはまるものであり、現実の世界でも同様です。
私たちの日常の中でも、「母としての自分」「部下としての自分」「昔の恋人に再会したときの自分」など、
立場や関係性によって態度や言動は自然に変わっていきます。つまり、行動が役割を映し出しているのです。
態度も変わり、怖い色も変わり、目の奥から変わりますよね?
このことから、演技においても「行動が何者なのかを決める」という視点が非常に重要になることが、実感できると思います。
2:繰り返している行動にこそ、“その人らしさ”が出る
セリフ以外が実はコア!
確かにしゃべることも「行動」ではあるのですが、言葉を嘘をつくことがたやすいです。
これは近年の研究でも証明されていることで、多くの学者や研究者が発表しています。
例えば、家族内での父親や祖母、あるいは学校や地域コミュニティ内でのリーダーや聞き役といった役割は、意識していなくても、繰り返し取る行動によって自然と形づくられていきます。だからこそ、気をつけなければいけない。
行動から性格が作られる、と言う側面もありますから。
そして、作品の世界でも、何気ない動作や言葉の使い方、視線の向け方などに「役割」が織り込まれています。これらを丁寧に読み解いていくことで、「この人物はこういう関係性の中にいる」という解像度が高まります。
くっきり、はっきりしてくるわけです。
そしてそれは、その役が“誰なのか”を演じる上での指針となり、
結果的にセリフになっている「言葉が必要になる」、という順序だと考えられます。
特に、台本上で“繰り返されている行動”には注意が必要です。
同じ人物にだけ強く当たっている、ある話題になると黙ってしまう、何度も同じ言い訳をしている
——そうした行動の反復は、演じる役の役割や立場、さらには相手に対してどのような態度を取っているのかを如実に表しています。
多くの俳優が「演技力=感情表現の豊かさ」だと誤解してしまいがちですが、
フィクション(及びドキュメンタリーなど演出されて再構築されたもの)にリアリティーを伴わせるには、
“関係性の自覚”と“再現可能な行動”です。行動から感覚も引き起こされ、行動から意図や動機も伝わります。
さらにそれが、何度繰り返しても深まっていく演技に繋がります。
私たちの中でも、「何度見ても信じられるSci -Fiフィクション」
繰り返し見てはワクワク&ドキドキする本当はありえないような設定の「ロマンチック!ドタバタ・コメディー」ありませんか?
例えば、私は、小学生の頃まで、ジュリー・アンドリュース先輩の「メリーポピンズ」映画版(最近のエミリー・ブラントのバージョンではなく初代です)大ファンでした。
小学校から帰ると、ビデオを再生しては毎週見ていました。
あらすじからして、冷静に考えれば、全く信じられる事項はほとんどないのですが、
役の人物たちの様子、自分が自分をどう感じているか、そして周囲(子供たちや大人、想像上の生き物や環境)どう感じているかが、リアリティーを持って感じられて、現実の世界以上にワクワクした記憶があります。
そうなんです、ジャンルによっては、「役の行動が信じられるかどうか」であり
「現実と似てるかどうか」では無いのです。
3:「なんとなく演じる」では伝わらない理由
無意識は、作品の力を停滞させる
これは、ご自身が自覚してらっしゃらない場合もあるので、とても難しいのですが、
私は自己洞察が深まれば深まるほど、作品の創作が他人と協力しやすくなり、また現場での意思疎通もスムーズになると考えています。
もしこの役の人物自身が「誰なのか」を曖昧なままにしてしまうと、役としての立場や関係性が一定のまま停滞し、シーンが平板に見えるだけでなく、相手役との関係の変化も描きづらくなります。
これは俳優だけでなく、作家、演出家、監督の方もそうなのではないでしょうか?
(さらに言えば、人物像が深く、具体的にわからなければ、衣装やヘアメイクも難しいはずです)
たとえば、
あるシーンで“上司”として振る舞うべき人物が、無意識に“友人”のような口調で話してしまうと、観客や視聴者は「この人たちは何の関係なのだろう?」と混乱するか、あるいは役柄そのものの解釈が不明瞭になってしまいます。(それが狙いの場合は別です。)
また、「誰なのか」を放っておくと、演者自身の気持ちや考えが動かなくなり、セリフが“口先だけの言葉”になってしまうこともあります。これは特に、経験豊富な俳優に多く見られる落とし穴でもあります。
「せっかくの大事なセリフを流暢に喋りたい」、「滑舌が悪いと言われたくない」というのも、お気持ちはわかるのですが、ドラマの世界で生きている当事者たちには関係のない考えです。
特に、経験が増えてくると、基本的な技術だけで“なんとなくできてしまう”がゆえに、
「この行動は、誰として行っているのか?」という問いを改めて立てる機会が失われがちだからこそ、
実は、すごーく差がつくところです。
・過去の自分像
・現在の自分像
・未来の自分像
これだけでも世界が深まっていきませんか?
またよく話題になるのですが、「現場でダメ出しが出ない」ことが、
実は“役割の解像度が低いままOKをもらっている”状態である可能性もあります。
だからこそ、プロであればあるほどこの問いに立ち返ることが重要です。
特に中堅の方、いろいろな意味で評価が分かれる岐路に立っている方、見直してみてください!
4:「誰なのか」が見えた瞬間に、セリフが血を通う
“感情”は、行動と目的、そして役割が運んでくる
逆「誰なのか」を具体的に設定することで、行動の選択肢が具体的に、かつ立体的になります。
たとえば、同じ「ありがとう」というセリフでも、「自分が後輩」であるときと
「相手を励まそうとしている親友」であるときでは、声のトーンも、目線も、身体の角度も変わります。
例えば、私の大先輩は、本当に素晴らしいプロデューサーで俳優としての経験も豊富なまま会社を立ち上げたりとても精力的なのですが、いつも私に「すごいね」、「今日は誘ってくれてありがとう」、「いつもありがとうね」とおっしゃいます。
私は単純に、彼の態度を指摘したいのではなく、この言葉の背景にある彼の数多くの行動ー例えば、あちこちに観劇に行き、様々な方と交流し、率直に意見を述べ、論文を読み、実際に演出を研究し、読書し、さらにオペラやミュージカル、コンサートなど、幅広く、芸術作品にも触れしかも言語化していく…こういった実際の行動に支えられた言葉であるからこそ、気持ちが伝わり、私もそれに応えたいと感じるのだと振り返れます。
これは、演技だけでなく、私の昔からの専門であるムーブメントのレッスンやアレクサンダー・テクニークの個人指導でも顕著に見られる現象です。
ちょっとした立ち位置の変化や、相手との関係性における自覚が、呼吸や重心の置き方を変え、最終的には声の響きまで変容させていきます。
身体が構えていれば、自分像も歪みます。余計な緊張を解くことができれば、相手との関係性も変わり、「自分にとって相手が誰なのか」も変化していきます。
これはドラマの世界でも同じではないでしょうか?
俳優の方だけでなく、歌手の方、ダンサーの方でも、その瞬間の記憶がある方多いのではないでしょうか?
つまり、「誰なのか」は、テキスト解釈やキャラクター分析だけではなく、
身体の使い方、呼吸、感情の立ち上げ方にも関わってくる——俳優にとっての全方位的な基盤だということです。
5:「誰なのか」を見つける3つの視点
迷ったときは“行動”にヒントがある
ここで改めて、「誰なのか」を見つけるための3つの視点をまとめておきましょう:
・繰り返している行動:同じ人物や話題に対する反応のパターン、生活様式、いわゆる習慣
・所属するコミュニティや立場:職業、社会的な地位、家族、職場、コミュニティー、文化的背景など
・相手にとっての自分の役割:「母」「部下」「ライバル」など、関係性の中での自分(過去・現在・期待している未来、期待していない未来)
これらを台本書かれている事実から丁寧に整理していくことで、
役としての“誰なのか”が輪郭を持ち始めます。
そうすれば、ジャンルや必要に応じて「正体を明かす」こともあるでしょう。
楽しみになってきましたか?
オンラインでの台本読解及び分析のクラスも開催しています
おかげさまで、2023年に世界最大の専門団体IDCから取得したインティマシー・コーディネーター(ディレクター)のご相談もあり、映画などのリハーサルや撮影もあり、毎月というわけにはいきませんが、遠方の方や海外在住の方にも受講していただきやすいよ、オンラインでの台本読解のクラスも開催しています。
ときには、古典の名作を使って、場合によっては、映画の脚本や小説を使っての、「演じるための読み解き」の切り口を提案しています。
今回書いたような「いつ・どこ・誰?」にスタートし、いわゆる「目的」の設定や、どうやって役の人物を深めていくのか、自分と重ねたり、また適切な距離を作ったら際立つのか、また演技の役に立つのかを解説しています。
オンラインで台本読解を事前に済ませておいてから、スタジオでの演技の実践のクラスに進みますと、多くの方が、「時間が節約できてよかった」、「1人で変な方向に進まないで済んだ」、「事前に一緒にやっておいたから、安心してすぐに演技に取り組めた」と笑顔でおっしゃいます。
こちらのブログでも、クラスの紹介を進めていきますので、
気になる方、もっと飛躍したい方、我流で悩んできた方はぜひフォローしてください。
セリフ、それは結果の一部!
「時間」や「場所」が具体化すると、登場人物の行動は立ち上がりやすくなります。
同じように、「誰なのか」が明確になることで、登場人物の選択や決断がリアリティを持ち始め、物語が動き出します。
演じ手である俳優や歌手、ダンサーの方が、途端に生き生きとして、動き始める、これも嬉しい瞬間はありません。
ご本人も、重荷が降りたのか、過剰なプレッシャーから解放されたのか、本来の力を発揮して、のびのびとご自身の役割を果たし、また周囲をゆっくり見て感じる余裕ができて、輝き始めます。
私の個人レッスンやクラスでは、この「誰なのか」を起点に、行動や目的、感情のリアリティを総合的に磨いていきます。だからこそ、台本が“自分の身体を通して語り始める”感覚に変わるのです。
これは、私の日本での演技の先生が、常日頃からおっしゃっていたことでもあり、イギリスの演劇学校でもしつこく言われたことです。(本当にしつこかった…)
ご案内
Instagramでは、簡潔なQ&Aや短いリールを更新しています。お役に立てるとうれしいです。
https://www.instagram.com/actingcoachkaorukuwata/
取り上げて欲しいモヤモヤ、前から気になっていたことも募集しております。
最新情報
今回の内容に「もっと知りたい」「いつか参加したい」と感じてくださった方へ。
次回のクラス案内はInstagramとLINE公式で最速でお届けしています。
ブログにももちろん詳細を書きますが、少人数制で予約が埋まりやすいため、速報は公式LINE及びストーリーズの方から、現在は出しています。
Instagram → https://www.instagram.com/actingcoachkaorukuwata/
これまで触れてきた演技のなんとかメソッドや、〇〇式に疑問を抱かれた方へ
あなたの違和感は、もしかすると「役」にとってのリアリティーではなかったからかもしれません。
また文化的にも、ヨーロッパで過ごした20代がある私、そしてバイリンガルである私が言うのもなんですが、
日本を中心に活躍してらっしゃる方、日本語を母国語として多くの時間を過ごしてる方に向き不向きという傾向はある気がいたします。
物語、演技と言うものが、文化に根ざしている以上、やはり言語の壁もあり、また生活様式や基本的なコミュニケーションのスタイルが大きな誤解をむこともございます。これはクラシックバレエやオペラの輸入、様々な業種での変遷を見ても、お分かりいただける課題だと思います。
不可思議なワークショップやらの誇大広告に疑問、持たれた方、なんちゃらメソッドに違和感を持たれた方、ご自分のせいだと責めないでくださいね。
こちらの記事も、ご参考になればうれしいです。
「セリフに気持ちは『のせないで』ください?」— これが演技のリアリティを変える
「今回は どうしてもスケジュールが難しいけど、次回のクラスを知りたい」という方は、
公式LINEに登録 or Instagramもフォローしておいてください!
📩 次回の優先案内を受け取る →https://lin.ee/2HZK7jV
「現場での課題について相談したい」「オーディション対策の個人レッスンを申し込みたい」「身体や呼吸のことから見直したい」という方も、上のフォームよりお気軽にご連絡ください。
事務所・マネージャーの方で、「所属俳優にレッスンを受けさせたい」「講師として招聘を検討したい」といったご相談も歓迎しています。オンラインでのヒアリングも可能です。
お急ぎの方には公式LINEもございます。こちらからのトークのスタートはできませんので、一言ご挨拶かスタンプお願いします。
公式LINEからのお知らせの一斉送信は月に1回程度、 多くて2回程度です、ご安心ください。
このブログでは、今後も
・台本読解や演技へのアプローチのヒント
・現場で役立つ準備の方法
・実際のクラスからの気づきや実例
…などを定期的に発信していきます。
ぜひ、ブックマークしてまた読みにきてくださいね。
個人レッスンも受付中ですが、4月の新規受付はごく限られた枠のみ。ご興味がある方はブックマークかフォローをおすすめします。
次回記事では、「行動と目的」を掘り下げて解説する予定です。
「なぜ自分は今この行動をしているのか?」を明確にすることで、演技はさらに深まり、相手との関係性も生きたものになります。
これはミュージカル、オペラ、演劇に限らず、映画やテレビ、コマーシャルでも使える視点です。
みなさんのご活躍、楽しみにしています。
最後に最近、芸能関係、映画関連の方からよく聞かれるトピックー
ご参考になれば幸いです。
演技の違いを生む②「セリフの奥にある意図」を見抜く方法

演技コーチ/ムーヴメント指導・演出・振付/IDC認定インティマシーディレクター/STAT認定アレクサンダー・テクニーク指導者/スピーチ&プレゼンテーションコーチングActing Coach/Movement Direction/IDC qualified Intimacy Director/STAT certified Alexander Technique teacher, mSTAT, Movement Teaching/Speech and Presentation Coaching