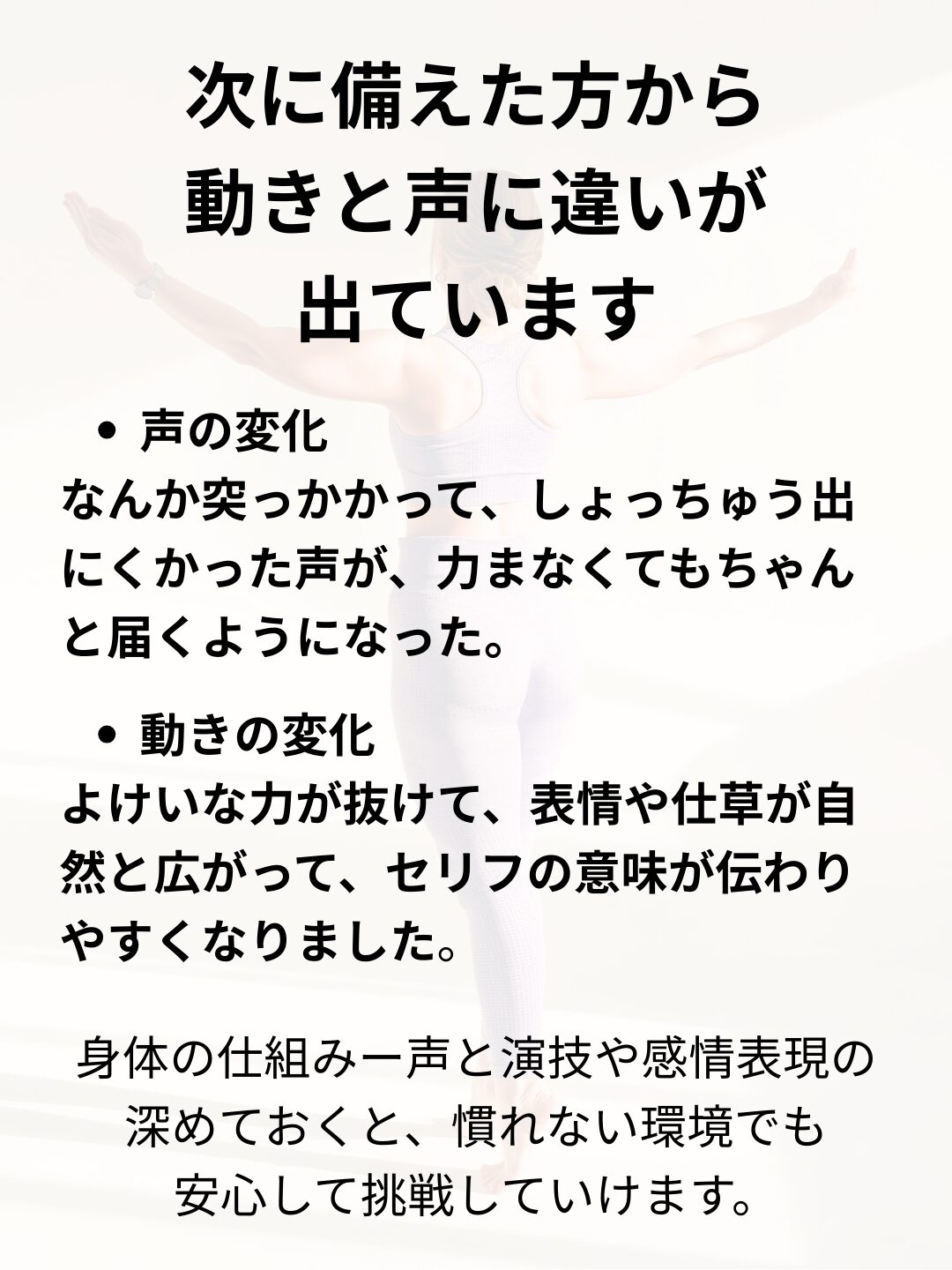秋の夜長は読書もカフェも嬉しい、演技コーチの鍬田かおるです。オーディションシーズンもまだまだ。個人レッスンを毎週続けております。特にミュージカル、オペラ、演劇、映画の方々の成長が目覚ましく、私も鼻が高いです。
さて、本日は、ちょっと視点を変えて。
“だから”と“にも関わらず”が演技の構造を変える理由
同じ言葉でも、前提や文脈が異なれば、行動と意味はまったく変わります。
“だから”は進行の文脈、“にも関わらず”は矛盾と深まりの地点。
これをつい忘れてしまい、セリフそのものの意味を信じてしまうと行き詰まります。
なぜなら、当たり前すぎますが、何らかの出来事が起きる時、ズレが生じてるんですよ。
作品はおうおうにして、ワクワクしたり、ハラハラしたり、ドキドキしたり、一緒に泣いたり笑ったり…ということですから、並列の、ある意味、率直な、ありのままの言葉のやりとりでは無いのです。
またセリフは感情の出口ではなく“途中の現象”です。結果の一部といっても良い。
台本読解と想像では「言葉が生まれる事情」を読む力が必要です。
同じ言葉でも、構造が違えば意味が変わる
“だから”と“にも関わらず”は、どちらも単なる接続詞ですが、演技においては人物の構造をまったく異なる方向へ導きます。
“だから”は【進行の文脈】を表し、状況の流れに自然に従う行動。
この進行は、素直とかありのままにも見えますが、必ずしもそうは限らないので、要注意です。目的に向かって、目標に進んでいると言う意味で進行なのです。
“にも関わらず”は【矛盾と深まりの地点】を示し、痛みや葛藤を抱えながらも行動する構造です。必ずしも進行しているわけではなく、深まっていく考えや問題、発展はしているが、目的には近づいていなかったり、障害が生じている状況も含まれます。
現場の経験が多い方、様々なドラマを体験してきた方は、ご存知ですよね?
と、いうわけで、一見同じにみえるセリフでも、どの文脈で発されているかによって、人物の在り方が大きく変わります。
だからこそ、身体も変わる、そして声も変わります。
“だから”で動く人物と、“にも関わらず”で動く人物
同じ「行かなくちゃ」というセリフでも、
“だから行かなくちゃ”は流れに沿う行動、国語の意味とそこまでギャップがありません。
一方、
“にも関わらず行かなくちゃ”は抵抗や痛みを含んだ行動です。何か拮抗している、別の力が働いています。
この違いは、観客が受け取る印象や聞こえる音への影響を大きく変えます。
ですから、演技の深みは単なる感情の強さやボリュームではなく、「どの構造から行動しているか」という読み取りによって生まれます。
ここ、類推やメタファーも使えるところですね。
台本読解と分析でで“言葉が必要になる事情”をほどいていこう
セリフを表面的に読むのではなく、「なぜその言葉が生まれたのか」を探る。
それもただ探るだけではなく、実際に動いてみて感じるんです。
台本に書かれている部分から、書かれていないところまで、その背景を読み解くことで、人物の思考の層や、行動に潜む矛盾や密かな願望、欲求も見えてきます。
面白いのは、役の人物自身も、おそらく意識してない部分がはみ出てきた時…、エキサイティングです。
という意味では、演じ手側は、役の人物が、自分自身を理解している以上に、役の人物のことを掘り下げている可能性もありますね。
俳優に必要なのは、ただ感情を演じるとか出す力よりも、“言葉が生まれる構造”を想像力と組み合わせながら、抽象と具体の間を生きして、その場で、感じ取る力です。そして行動していく。
その一歩が、台本読解の本質であり、演技のリアリティーを支える土台となります。
(作品のジャンルや、極端な例によっては、フィクションの構造を使ってご自身の心身を守ることにもつながります。)
構造を読む力が、演技を変える
セリフを感情で捉えるのではなく、行動の構造として扱う。
“だから”と“にも関わらず”というわずかな違いの中に、人物の意志や矛盾、そして生きたリアリティが潜んでいます。
こうやって言葉により自覚的になること。
そこから「深く読み込む」「想像を膨らませる」が加速していきます。
台本を読む時、言葉の奥にある“事情”を探すこと。
しかもそれは、固有のものであって、一般化された平均的かつ、必ずしも飲み込みやすいものばかりではありません。
にもかかわらず、それができる俳優は、観客の記憶に残る存在へと変わっていきます。
10月の俳優や歌手の方を中心とした演技のクラスはこちらです