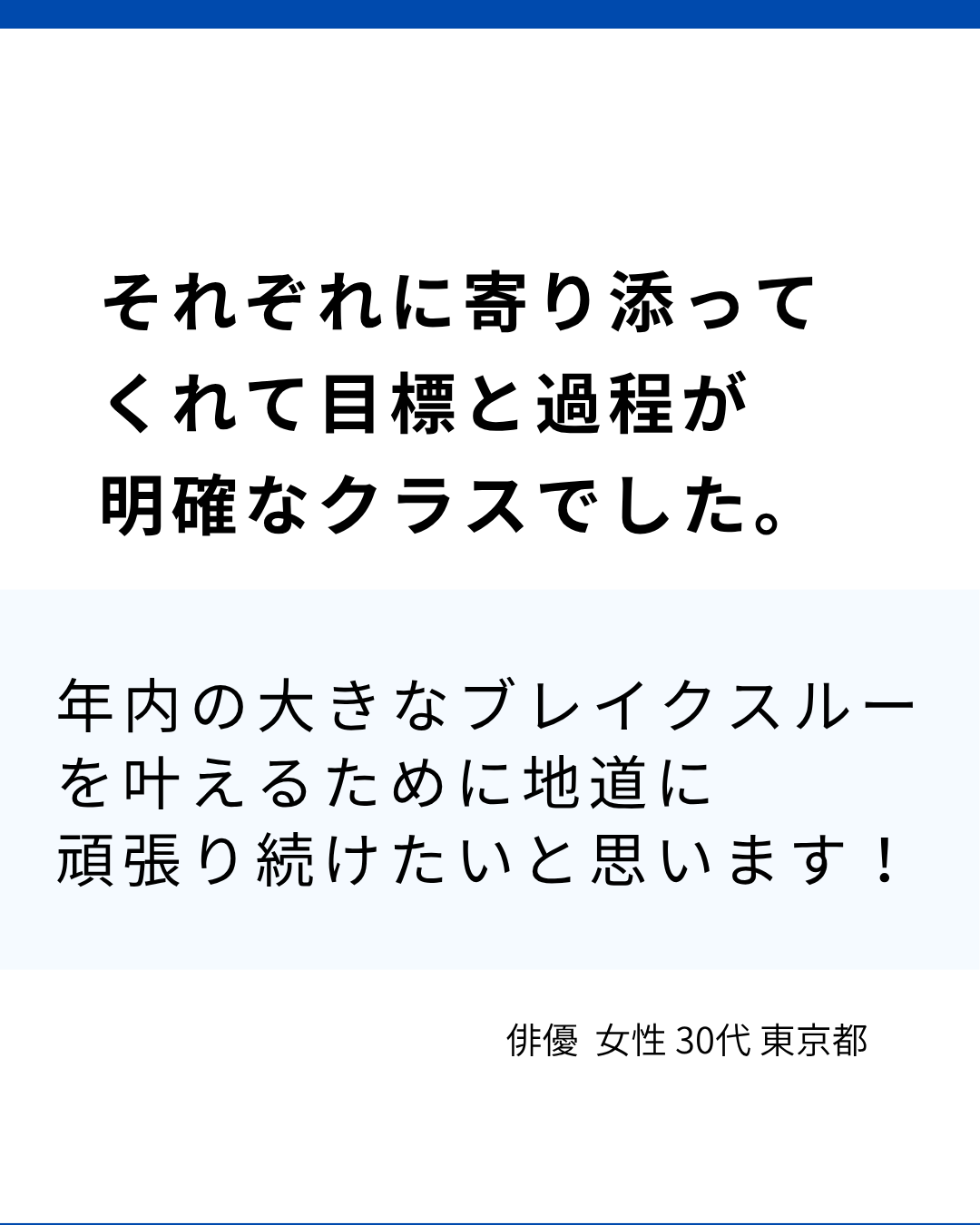感情を“出そう”と意識すると、演技がどこか「わざとらしく」見えてしまう——。
プロの俳優でも、そこに無意識で陥るケースは少なくありません。
感情をご自身が感じるだけでなく、伝わる「選択」が明確な演技こそ、リアリティにつながる鍵です。
こんにちは、夏の企画が目白押し、楽しみが膨らむ、演技コーチのくわた かおるです。
最近は、IDC認定インティマシーコーディネーター(ディレクター)のお問い合わせもいただき、ヒアリングに続き、映像や、舞台作品のご相談にも対応しております。
本日は、避けては通れない台本読解を整理します。
すでに現場があって活躍してらっしゃる方でも、さらにレベルアップ。忙しかったりすると、つい時々忘れてしまう点もあるかもしれませんので、リマインダーとして活用していただければうれしいです。
演技の準備と聞くと、台本を何度も読み込むことと思っていませんか?
もしくはセリフを覚えて、所作をイメージして、なじませておくこと、みたいな感じ。
もちろん、それらも大切な作業です。
でも、ただセリフを覚えたり、口調を整えたり、所作を把握しておくだけでは、
“その人物”はまだどこにも存在していません。
たとえば、こんな経験はありませんか?
・セリフは覚えたのに「なんだか薄い」と感じる。
・慣れれば慣れるほど、新鮮味が薄れていく…
・感情を込めているつもりなのに「芝居してる感じ」と言われる。
・いろいろ考えていたら、「あなたらしさがない」のような指摘をされる。
・相手とのやりとりが、なぜか“噛み合っていない”らしい——。
それは、セリフや表情よりも先に、
「この人物は『誰』なのか?」という視点が抜けてしまっているのかもしれません。
そうなんです。「誰」=何者なのか、です。
違和感、ありますか?
「この人物はどんな人なのか?」が日本語の文法的に正しそうですよね。
私も、子どもの頃から演出家や俳優の先輩たち、ディレクターから「どんな人なのかわからない」とツッコまれていました。
しかし日本語で「どんな?」「どのような」と聞かれると、ついその流れで
「形容詞で様子」を考えてしまうんです。
「ニコニコしてて、明るくて、颯爽としてる」とか
「気難しくて、しかめっつらの時があって、ちょっと頭が固い」みたいな感じ。
これが行き詰まる原因であり、解像度が低くなり、時間がかかってしまう要因の1つです。
・自分が演じるその役は、一体どんな人生を歩んできたのか。
・この場面に至るまで、何を感じ、何を背負ってきたのか。
このように、導いてくださる方や、演出や監督から尋ねられていた時、どうしても文学のように、そしてお客様目線で外から描写してしまうとき、ありませんか?
ある程度経験のある方であれば、そうした背景に想像を巡らせずにセリフを読んでしまうと、
演技はどこか「説明的」に、浅く、平面的になってしまう事は知ってます。
それにもかかわらず、「『自分事として』行動する」という視点に、素早く映るための質問を組み立てるに至っていない。
そんなことをイギリスでも、そして日本で指導し始めて6、7年ぐらい、日々考えていました。
役の人物像を「性格」だけで捉えていませんか?
「この役は気が強そうだから、声は大きめで、語尾を強くしよう」
「優しい役だから、柔らかく演じよう、ニコニコしたほうがいいかな?」
演技経験が増えるのに比例して、もちろん感覚も良くなっていくので、つい私たちはわかりやすく「性格のようなもの」で人物像を処理してしまいがちかもしれません。
分析すると、おそらく性格を外から描写する時「形容詞」になってしまいがち。
これは私がさっき書いた通りです。
例えば「すごく優しい人」、「情熱溢れる頼もしい男性」のような感じ。
間違ってはいないのですが、それだけでは役の“奥行き”が足りないのです。
また、本人の認知や心象風景とも実は違います。
どこか説明的で、平面的な演技になってしまうのは、そして演技にムラがあるのは、
その視点がまだまだ「お客様」だから。
そして演出家や共演者から、こんな風に言われたりします。
「もっとその人になって」「考えて動いて」
「なんか“芝居してる感じ”に見える」
「もっと自然に!」(これほんとに、困りますよね…)
ここがお客様目線のままだと、どうしても行き詰まってしまうので、キャリアの長い方もちょっとお付き合いくださいね。
セリフの裏にある「その方の『個人的な』事情」を深掘りませんか?
演じるということは、セリフを気持ちを込めて言うことではありません。
ましてや、「その状況に合うように(よくあるという意味)振る舞って、気持ちを発露すれば、良いということでもありません。ここもほとんどの経験者を知っている。
実際、「セリフにはなってない部分」を含め、書かれていない部分を想像し、動き、交流し、しゃべり、感じながら、実際の人物かのように、立体的にあらわにしていくことです。
これも、理屈では理解している方が多いです。
だからこそ、説得力もあり、役のリアリティーもある。
たとえそれが、近未来の設定やファンタジーであったとしても、フィクションであるにもかかわらず、その時間は「信じるに値する」んですよね。
例えば、役は
・なぜその言葉を選んだのか?他に言える事はなかった?
・なぜそのタイミングで言ったのか?今じゃなきゃいけない理由は?
・なぜ黙るという選択をしたのか?昨日は言えなかったの?来週ならどうする?
その「なぜ」の連続が、演技のリアリティを作ります。
たとえば——
・口調がきついのは、自分の弱さを悟られたくないからかもしれない
・優しく微笑むのは、謝るよりもその場をおさめたいからかもしれない
・黙って立ち去るのは、怒りではなく、絶望からかもしれない
人物の行動や選択を、自分の身体で再構築・擬似体験する、に近いかもしれません。
そのとき初めて、
・「この人はこういう出来事があった(かも)」
・「全然、違うものを見てる」
・「同じ言葉のはずが、全然違う意味に聞こえるんだ」
と腑に落ちる瞬間が訪れます。
だから、形容詞じゃなくて「動詞と名詞」が鍵です。
という事は、「この役(人物)は誰なのか?」は、
「どんな・どのような」ではなく、
おそらく「何なのか・何者か?」にした方が、理解が早く、距離も近くなるのです。
(日本語の文法的に違和感があるというご意見はごもっともです、ただ私は現場での実践の話をしています)
私自身、日本で指導を始めてからも、もちろんイギリスにも時々、研修や観劇などで戻ったりもしていたのですが、ある時、オーストラリアとロサンゼルスで演技コーチの師匠と出会います。周囲の若手の俳優が悩んでいたこともあり、そこから日本で日本語でより効率的に教えるための、台本読解と分析の整理に本腰を入れてスピードを上げました。
「見え方や印象」ではなく「行動」で人物をとらえることから
日常生活で、私たちは(おそらく)人の性格を直接見る事は難しい。
間接的に、“行動”を通して、比べたり、意味を想像したりしながら、判断しています。
たとえば初対面の方が——
・目を合わせずに話す、下を向いている
・笑いながらも手が落ち着かない、携帯ばかり触ってる
・先に立ち上がった
それらが積み重なって、「いまなにか心配?」「もしかしたら急いでいるのかも」と情報を総合的に集めながら、意味を考えていきます。(無意識で行われる部分も多いね)
もちろんそれが外れることもあるんですが、口から発せられる言葉以上に、動きと言うのは、嘘をつきにくいもの。
演技も同じです。
「優しい人だから優しく(と自分が思っている行動を)する」ではなく、
「その場面で、その選択をした理由」が腑に落ちていると、行動から“人物像”が立ち上がります。
逆に
よくある「自然にやろう」と考えてしまうと厄介
なぜなら、作品の世界での「自然=その世界であり得そう」は必ずしも「自分の身近にある」「たまたま日常で自分が見かける」「自分にとって慣れている」という意味ではないからです。
例外はもちろんありますが、物理的にかつ科学的に、「他人として存在する説得力がある」「信じるに値するストーリーがバックグラウンドにあると思わせてくれる」ということ。
つまり、感情的に「時間や労力」を費やしたいと思わせてくれるかどうか、テーマに沿って、人物を「あらわに」して、まるで実際に存在する人物「かのように」感じさせてくれるからこそ、疑問の対象であり、怒りの対象にもなり得て、かつ共感することもできるわけです。
これは言語だけでカバーできるものではないですし、動き(及び周囲)との相関関係が常に働きます。
となると、冒頭の質問
「この役の人物は何者なのか?」
「この(相手の)役は誰なのか?」
を飛ばして、結果としての、歩き方や喋り方を先に決めてしまうと行き詰まるのです。
その人が「何を見て」「何を大事にしているか」から
数々の舞台作品や映画などを通じて、私も日々考えておりますが、演技で最も伝わるのは、実際のセリフではないかもしれません。
ここが文学と違うところ。
その人物が「何を見て、何を信じ、何を避け、何を守ろうとしているか、
今、「何が緊急なのか、どんな方法で問題を解決しようとしているのか」。
すごく具体的で、現実の世界での私たちとそっくりの仕組みですよね。
・その人は、どこで、自分より他人を優先するのか?それは何がきっかけ?目的は?
・いつ、どんな傷を負って、今の行動を選んでいるのか?何が防衛? 1番恐れている事は?
・本当はどうしたかったのに、何をあきらめたのか?という事は、実際、何を選んだの?
こうした、「現実の世界で無意識ながらも私たちがやっていること」に忠実に、想像をめぐらせると、セリフや動きは影響受けて、無理に力を込めずとも、変わっていきます。
それこそ自然と、呼吸や間合い、視線、あらゆる強弱も変わるのです。
これらは、頭で1人で妄想することではなくて、身体動かして、実際に行動しながら声を出してみて気づいていく、オーガニックなプロセスです。
頭で考えるだけじゃなく、でも身体でただなんとなく探るだけじゃない。
両方が組み合わさって、相乗効果を見出します。
だから現場に強い、応用が効く、でも自分の感性やこれまでの体験も使える、そんなプロセスが現代の生き生きとした演技には有効です。
台本を読んだら、まずやるべき7つの問いかけ
では、具体的にどうすれば良いのでしょうか?
私のレッスンでは、役作りの導入に次のような問いを立てています。
-
空間:この人は、どこで生きてきたか?どこから来て、どこに向かうのか。
-
欲求:今、この場面で「何を得たい」と思っているか?そもそも自分にとって相手は誰なのか。
-
恐れ:何を恐れているか?何を避けようとしているか?それはなぜなのか?相手にとって自分は誰なのか。
-
時間: いま、いつなの?「いつといつの間?」そしてこのセリフを、今、なぜこのタイミングで言うのか?もし言わなかったらどうなるのか?
-
内面/欲求/願望:黙っている時間に、どんな思考が流れているか?何が腹の底の叫び?密かな願い?
-
誰:もし別の状況なら、この人はどうしたか?本質的にどういう生き物なのか、何者なのかということ。(例えば何でお金を得ているか、長い時間何をしているか、ですね。)
-
種:自分自身の中に、この人物と重なる部分はあるか?(もちろん、仕事なのに全く重なる部分がないので、キャスティングされる事は稀です。)しかしながら、キャスティングされた以上、自分の中に、その役の人物「芽🌱」を見つけるのは演じ手自身の責任の範囲です。
こうした問いに向き合うことで、
その人物の“内側のロジック”や感情的なクセ、生い立ちの記憶、こだわり….
あえて大雑把に言えば「ライフスタイル」が見えてきます。
「セリフを読む」のではなく、「その人として喋る」
セリフは、“思考の結果”です。
しかもその世界でオーケーとされている「既に検閲された言葉。」
人は、考えて、感じて、迷って、選んで、そして初めて言葉にします。(もちろんうっかりもありますが、それは何らかの意図や動機や無意識が働いているのが、創作の世界です)
つまり、「言いたくて言う」のではなく、
「言わざるを得なくて言っている」瞬間が、リアリティを生むのです。
これは役の人物が、今まで通り、いつも通りの自分の言動を続けていられないから、ドラマを起きている仕組みと同じです。
感情を出そうとするよりも、そしてセリフをどんなふうに言うかよりも、
「なぜ今これを言わねばならないか」、「なぜこれらの言葉が必要なのか」に立ち返ったとき、
本当にその人物として“行動する”演技が始まります。
だから「この(特定の)相手にとって、自分が誰なのか」
今、「自分にとって相手が誰に変わったのか」
というシフトが起きます。
すごく面白いですよ。
現場で信頼される俳優とは?
演出家や監督が安心して任せられる俳優は、共通して“準備”ができている人です。
・「この人のこと、ちゃんと掴んでるな」と伝わる
・ただ受け身ではなく、自分の中に選択肢を複数、持っている
・相手との関係性を、自分の身体から、呼吸や声から作っていける
それらは、すべて【人物理解】と【行動の選択】の積み重ねから生まれます。
自分が頭の中で考えてきたことにこだわり続けるのも、一緒にはやりにくい。
かといって、相手にアドバイスをもらって、何か提案してもらうのを待ち続ける方…これも一緒に取り組むはずが、とっても非対称です。
感情を出そうとする演技が浅くなる理由と、選択で深める方法は
「悲しそうにしよう」ではなく(実際そういうふうに生活してないですよね?)
「悲しいとき、この人にとって「自分は誰」、自分にとって「相手は誰」だから、どの行動するか?」を考えてみませんか。
そして、次のステップに進みます。
例えば、自分の役の立場が「困っている【にもかかわらず】」台本に書かれている行動を取るのはなぜなのか?
つまり「何が自分を〇〇(行動)させるのか?」なんです。
だからこそ、どんなセリフも、どんな状況も、
その人の人生を生きていれば、自然と複数の意味を持ってきます。
そしてその深みは、必ずしも感動ではなくとも、疑問を呈したり、これまでになかった視点を与えたり、ときには反感を覚えさせて刺激したり、いろいろな形で観る人の心を確かに揺さぶるのです。
このように「いつなのか・どこなのか」に続いて
「誰なのか」もぜひ個人化・具体化してみてください。
きっと手答えが、変わってきます。
クラスやレッスンで「プロが人物を立ち上げる台本の読み方」を丁寧に扱っています
俳優として、歌手として、もっとリアルな演技がしたい。リアリティーを役に与えたい。
セリフの裏にある“人生”まで、感じられるようになりたい、そして説得力を持ちたい。
そんなプロのために、私のクラスでは
・台本に入る前の“準備”
・行動から人物像を立てる練習、方法を増やすヒント
・「なぜこの言葉を選んだか」の掘り下げ、役の人物の準備。
を、実際の題材とともにじっくり扱っています。
少人数制だからこそ、個別のつまずきにも丁寧に向き合えます。
単発のキャスティングを目的としたワークショップや、出演をお約束する監督や演出のクラスとは異なりますが、まだキャリアが浅いからこそ大事に積み重ねていきたい方、継続的に底力アップさせたい経験者の方、基礎を見直して飛躍したい活躍中の方も歓迎しております。
今の演技に違和感や伸び悩みを感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。
(演出家や監督、脚本家の方のご相談にも対応しております)
▶︎今月中にお問い合わせフォームから個人レッスンまたはグループクラスをお申し込みいただいた方には、
【台本分析 × 動きの整理】をテーマにした夏の特別セッションを優先してご案内しています。
もしよろしければ、ぜひどうぞ。
▶︎個人レッスン/グループクラスの詳細の確認
クラス・レッスン
「読むだけ」では終わらせない。
あなたの演技に“変化の準備”が必要だと感じたら、いつでもお待ちしています。
●この記事を書いた人:鍬田かおる :
演技コーチ/インティマシー・コーディネーター(ディレクター)
演技指導歴20年以上。プロ俳優・歌手・ダンサーを中心に、基礎から応用、身体とムーヴメントや台本読解など、幅広いアプローチをつかった指導を展開中。映画スクールやパフォーミングアーツの大学を始め、多様なミュージカル、オペラ、映像、舞台など幅広い現場でも指導。
詳しいプロフィールは、HPのプロフィールページにもございます。
こちらの記事で、目が覚めた!という方もいらっしゃいましたので…
「まず状況を成立させることが大事」と思っていませんか? 演技を“浅い”と言われてしまうときの見直しポイント
最新情報
今回の内容に「もっと知りたい」「いつか参加したい」と感じてくださった方へ。
次回のクラス案内はInstagramとLINE公式で最速でお届けしています。
ブログにも詳細を書きますが、少人数制で予約が埋まりやすいため
速報は公式LINE及びストーリーズの方から、現在は出しています。
Instagram → https://www.instagram.com/actingcoachkaorukuwata/
これまで演技のなんとかメソッドや、〇〇式に疑問を抱かれてきた方へ
あなたの感じてきたモヤモヤは、もしかすると「役」にとってのリアリティーが
具体的で意味のあるものではなかったからかもしれません。
また大学、演劇学校、大学院と、イギリス育ち、バイリンガルである私が言うのもなんですが、日本を中心に活躍してらっしゃる方、日本語を母国語として多くの時間を過ごしてる方にとっての、演技メソッドやシステムに向き不向きという傾向はある気がいたします。特に、
・真面目に考え込んでしまう方、好きだからこそ抱え込んでしまう方
・主語不在でも成立してしまう日本語の発想のまま、つい「状況を思い描き続けて」しまう方
・どうしても頭でっかちになり、言葉ばかりになってしまう熱心で真剣な方
・迷惑をかけてはいけないと、一生懸命ひとりで頑張りすぎる日本の俳優や歌手
……演劇だけでなく、映画、ミュージカル、オペラでもたくさん見てきました。
こういった方々に必要なのは、今日解説したような「身体と感覚」の入り口であり
想像していることと身体を馴染ませ、変化を歓迎して、他人と共感したり
同調したりできる身体を開くこと、事実をもとに、さらに想像力を飛躍させていくことです。
これらは、セラピー的なものでもなく、単なる精神論でもありません。
ダンスや楽器演奏のトレーニングに近い、1種スポーツのような
動きを切り口とした、感覚を伸ばし磨く、演技のトレーニングによるものです。
物語、演技いうものが、文化に根ざしている以上、言語の壁もあり、
また生活様式や基本的なコミュニケーションのスタイルが大きな誤解をむこともございます。
これはクラシックバレエやオペラの輸入、様々な業種での変遷を見ても、お分かりいただける課題だと思います。
不可思議なワークショップやらの誇大広告に疑問を持たれた方
なんちゃらメソッドに違和感を持たれた方、すべてご自分のせいだと責めないでくださいね。
(どこの国にも奇妙なマーケティングや不思議な我流は存在します)
こちらの記事も、ご参考になればうれしいです。
◾️7月演技クラス「台本読解と伝わる演技の実践」ーシーンの構造と演技に必要な身体
「7/20(日)7/21(月祝)のクラスに参加してみたかったけど、どうしてもスケジュールが難しい」
という方は、公式LINEに登録 or Instagramもフォローしてください。
📩 次回の優先案内を受け取る →https://lin.ee/2HZK7jV
「現場での課題について相談したい」「オーディション対策の個人レッスンを申し込みたい」
「身体や呼吸のことから見直したい」という方も、上のフォームよりお気軽にご連絡ください。
●事務所・マネージャーの方で、「うちの俳優にレッスンを受けさせたい」
「講師として招聘を検討したい」といったご相談も歓迎しています。
オンラインでのヒアリングも可能です。
お急ぎの方には公式LINEもございます。こちらからのトークのスタートはできませんので、一言ご挨拶かスタンプお願いします。
公式LINEからのお知らせの一斉送信は月に1回程度、 多くて2回程度です、ご安心ください。
このブログでは、今後も
・台本読解や演技へのアプローチのヒント
・現場で役立つ準備の方法、プロのブラッシュアップ
・実際のクラスからの気づきや実例
…などを定期的に発信していきます。
ぜひ、ブックマークしてまた読みにきてください。
個人レッスンも受付中ですが、5月中旬の新規受付はあと2枠のみ。
ご興味がある方はブックマークかフォローをおすすめします。
台本の読解、身体と声/呼吸、想像力、共感、そして論理的思考…
これらは活躍の場がミュージカル、オペラ、演劇に限らず、映画やテレビ、コマーシャルでも同じくです。
最後に最近、芸能関係、映画関連の方からよく聞かれるトピックーご参考になれば幸いです。
センシティブな題材、キスやハグなどの身体的な接触、いわゆる絡み、昔で言う濡れ場などの振り付け、演出サポートのご相談は、映像作品、映画、テレビ、舞台にかかわらず、下のインティマシー・コーディネーター(ディレクター)こちらのホームページからお願いします。

演技コーチ/ムーヴメント指導・演出・振付/IDC認定インティマシーディレクター/STAT認定アレクサンダー・テクニーク指導者/スピーチ&プレゼンテーションコーチングActing Coach/Movement Direction/IDC qualified Intimacy Director/STAT certified Alexander Technique teacher, mSTAT, Movement Teaching/Speech and Presentation Coaching